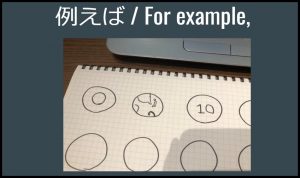「リーダシップ・フォロワーシップ、合意形成」 科目群「リーダーシップ・グループワーク基礎 I<S>」科目「EGAKU」ワークショップを2020年8月1日に行ないました。
•科目分類/Group of Course:リーダシップ、フォロワーシップ、合意形成 / Leadership, Followership and Consensus Building
•科目名/Course:TAL.W502-01 リーダーシップ・グループワーク基礎I <S> / Fundamental Group Work for Leadership I <S>
•プログラム名/Program:「EGAKU」ワークショプ/ “EGAKU” Workshop
•ファシリテーター /Facilitator:長谷部貴美、伊藤宏美、中村綾子 株式会社ホワイトシップ / Kimi Hasebe, Hiromi Ito and Ayako Nakamura, White Ship, Inc.
•開催日時/Date & Time:1/Aug(Sat) 13:00-17:00
この文書は東京工業大学リーダーシップ教育院(ToTAL)のホームページに掲載される、授業後の活動報告書です。本来であれば前年度の佐野千尋さんが作製されたような、客観的に授業内容や活動風景を記述する「報告書」が好ましいのかもしれませんが、「活動報告の形式は自由」とのこと、そして予予(かねがね)東工大生は(女子美術大とのペリパトス・オープンギャラリー等の活動があるにもかかわらず)芸術への関心が薄いと感じていたこともあり、EGAKUワークショップ受講の推薦書を兼ね、芸術に関する私の「意見書」のような形式となっておりますこと、ご容赦ください。
私は芸術・アートが大好きです。その出会いは学部2年生の時にニューヨークのメトロポリタン美術館やアメリカ自然史博物館に行った時でした。そこで出会ったのは、ただただ美しい作品たち。見れば見るほど、作品にはどんな意味が込められているのだろうか、時代背景は、他の作品との違いは、等々興味は尽きませんでした。
アートとは決して難しいものではありません。もちろん、歴史や描き方の変遷、画材による違い、描く人間による違いなど知れば知るほど鑑賞や感じ方が変わっていき、楽しむことができます。しかしながら、私にとってアートとは突き詰めれば、きれいなもの・美しいもの、そして美しいと感じることに他なりません。自然の景色を見た時、花を愛でるとき、きれいな女性を振り向くとき(笑)には必ず「きれいだな」「いい気分だな」と感じることでしょう。もしくは「興味深いな」と感じる方もいるかもしれません。その時の心的幸福は何ものにも代えがたいもので、アートもそれと同じだと私は考えています。
そうしたアートに触れる機会といえば美術館に行って鑑賞することです(コロナ禍の前までは、私はほぼ週に一回美術館に足を運んでいました)が、やはり実際に絵を描いてみることで、描くことの難しさや、自分の美意識に基づく色彩配置を実験できることでしょう。
とはいっても忙しい大学院生にとってこれを行う時間も機会もあまりありません。EGAKUワークショップではアートを鑑賞・制作することに加えて、それらを同年代の異なるバックグラウンドを持つ人々と共有できます。そうした中で他者への共感や自己表現も養うことができると私は考えています。
EGAKUワークショップでは、アートの必要性や皆さんが持つ偏見を再考察したうえで、鑑賞ワーク、創作ワーク、グループ鑑賞ワークと進んでいきました。グループ鑑賞ワークでは小グループ内で自分の作品を見てもらい、コメントをもらったり、解説をしていく中で自分の思考や感性を広げていきます。アート作品の共有というのは話し合えば会うほど、新たな見方の発見があり、尽きないものです。欲を言えば、小グループでの作品共有時間をもっと欲しいと感じました。
創作ワークで、使う画材はパステルです。パステルというと幼児が使う簡単なものと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかしながらパステルは、ドガが次々と動きを変える踊り子を素早く描きとるために、ルノアールが優美で柔らかな少女像を描くために度々用いられた、歴史のある画材です。油彩が多いルドンも代表作「グラン・ブーケ」ではパステルを用い、色彩とほのかな霞が織りなす神秘的な世界を描いています。三菱一号館美術館にて常設展示してありますので、ぜひ一度ご覧になってくださいませ。


私もこのEGAKUワークショップで始めてパステル画を描きましたが、指を使ってぼかしたり、色を画面上で混ぜていくなど、かなり高度な技や感性を求められると感じました。パステル画に限らず、絵画技法を体験できる機会は少ないのでとても有意義に感じることができました。
今回の創作テーマは「わたしを突き動かすもの‐Things That Drive Me‐」ということで、そのテーマに沿ったパステル画を表現していきました。それにあたり、ホワイトシップの方々から事前にワークシートが配布されており、そこには自分を突き動かすものは何か、その根源は、色に例えると、といった具体的なチャートが示されており、自分の中でのイメージを整理することができ、とてもありがたかったです。
50分の創作時間で今回私が表現した「突き動かすもの」は、具体的なイメージではなく、抽象的な色の配置としました。様々な場面で私を突き動かす動機となるものといえば、「美しい」や「面白そう」と感じる気持ちだと考えました。
ということで、その美しい世界感を、自分の好きな紫色をベースに、さらにその上に自分が心地よいと感じる色を乗せていくことで表現していこうと思いました。イメージに合わせて配色をして定着スプレー処理をした後、作品を眺めてみますと少し殺風景な印象を受けましたので、試しに全体を白く塗りつぶしてみました。すると全体に霞がかった怪しげな雰囲気が現れ、興味深い、印象的な画面構成になりました。
しかしながら今度は配色した色がぼやけてしまったので、その上からまたスプレーした後に同じ色を乗せ、スプレー、白を乗せて…という風に5回ほど重ねていきました。最終的に原色の色を鮮やかに残しつつ、印象的な画面に仕上げることができた。作製していくうちに、イメージを描くのではなく、どれが心地よいか色を配置していく実験的な制作となってしまい、少し意図から外れたものになってしまったのかもしれません。本当はルノアールのようなきれいで柔らかなパステル画が描けたらいいなと思っていたのですが…。しかしながら、自分の持つ美意識や感性を再発見・再構築できたので、とても嬉しく思っています。
ワークショップをファシリテートいただいた、ホワイトシップのみなさん(長谷部貴美さん、伊藤宏美さん、中村綾子さん)に、感謝申し上げます。



今回はさらに、ホワイトシップの方々から木製の額の提供もあり、仕上げた作品を額装することもできました。額に入れてみると印象がガラッと変わるもので、より作品として客観的に鑑賞することができ、それによってさらなるブラッシュアップや方向性を模索することに繋がりました(写真は自宅にて額装した作品です)。
こうした、作品の鑑賞と共有だけでなく、作品の立案・作業・考察といった芸術創作活動の一連を体験できる機会はまず無いと思いますので、ぜひ多くの東工大生に参加してほしいと感じました。
余談ですが、今回はオンラインでの開催でしたが、他のワークショップ授業と比べてオンラインならではの利点もありました。グループでの鑑賞や共有にあたっては、相手の顔色や空気感があまり伝わらないので、率直な意見を言いやすかったです。また、一人でアート鑑賞をすることが多い私にとっては、周りの雑音を気にせず鑑賞ができたのも嬉しかったです。

長々と綴ってきましたが、いずれ皆さんがToTALに参加した折には、皆さんの感じる美しさ、そしてそこにかける思いをお聞きしたいものです。その日を楽しみに待っております。
(文責:加藤日向 生命理工学系 ライフエンジニアリングコース M2, ToTAL 2期生)