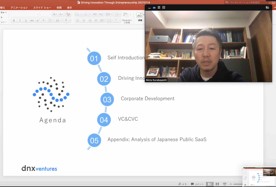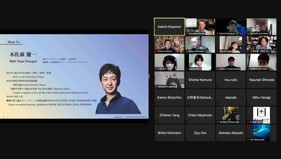ToTAL科目「プロフェッショナルと価値創造 II第7回:「社会インフラ分野における社会課題を解決する新事業の創生」を2021年1月29日に、ZOOMで行いました。
・科目分類:社会課題の認知
・科目名: TAL.S502 プロフェッショナルと価値創造 Ⅱ
・プログラム名:社会インフラ分野における社会課題を解決する新事業の創生
・ゲストスピーカー: 竹島昌弘、社会イノベーション事業推進本文事業創生推進本部デジタルソサエティ本部本部長、サステナブルインフラマネジメント部部長,未来投資本部インフラ保守プロジェクトリーダー 株式会社 日立製作所
・開催日時: 29 /Jan (Fri) 18:00-20:00
I. 竹島さんの話題提供:
- テーマ:新開発,水道管の漏水を検知する”超高感度振動センサ・MEMS”
- 概要:
2021年1月29日のProfessionals and Value Creation II #7にて,株式会社 日立製作所の竹島昌弘さんにご登壇して頂き,社会インフラ,特に地下埋設された水道管の老朽化問題に対応するための新技術や新事業創生などの軌跡について紹介してくださりました。竹島さんは日立製作所で社会イノベーション事業推進本文事業創生推進本部デジタルソサエティ本部本部長ならびにサステナブルインフラマネジメント部部長,未来投資本部インフラ保守プロジェクトリーダーとして従事されており,インフラだけでなく,これまでには日本初の高層ビル向け情報誌システムの開発や,世界初の民営刑務所向セキュリティシステムの開発など数多くの新事業に携われてきました。
今回は、ZOOMによるon-lineで行い、ToTAL登録生、及び、学部生4名を含めたOPEN生、合計24名が参加しました。尚、今回は、AGL/山田道場時代に頻繁にプログラムに参加され、日立に就職された日高さんのご尽力で実現したとのことです。


今回は、高度成長期に整備された数多くの社会インフラのなかでも主に水道管の老朽化問題について焦点を充て,これまで熟練の技術者の暗黙知的な「感覚」で検知されてきた地中の漏水問題をいかにテクノロジーで解決できないかという着想のもと立ち上げられた新事業の変遷と振動センサ(MEMS)の開発史について、我々学生の質疑に対応して頂きながら、紹介頂きました。
これまでの漏水問題の検知は数年の一定周期でメンテナンスを実施されてきましたが,その調査方法は熟練の技術者が音聴棒で確認するという方策がとられてきました。しかしながら,そのような専門技術者の数が近年徐々に減少を辿り,ここ数年で多く見受けられる道路陥没や大規模漏水などの問題が発生しています。漏水を検知できる技術者の減少という問題と,それらが検知される前に発生してしまう陥没などの諸問題という2つの事実を受け,竹島さんをはじめとした日立製作所はこれを今後の大きな社会課題として見据え,中長期的な観点に立脚した漏水検知センサの開発の取り組みを開始しました。
そこで開発されたのが日立製作所開発の超高感度振動センサ(MEMS)[以下,”MEMS” と表記]です。このセンサは従来の1,000倍の感度で漏水を検知し,尚且つ電力の低消費化を実現しました。従来は基本的に熟練者のノウハウに従い,点検もその解決もしらみ潰しのように対応してきましたが,このテクノロジー開発によって全国の至る所に,そして無数に地中に埋められたMEMSと無線基地局がIoT通信にて連携を組み,監視プラットフォームにて常時検知可能なシステムを構築することに成功しました。このシステムや技術は先進国および新興国においても高いニーズがあり,竹島さん率いるチームは実際に台湾やイタリアに現地調査を行い,現在は目下,先進国に向けたサービス提供を検討されているとのことです。
これまで外部と取り交わしたNDA、協定書、契約は役40件(小さなものを含めると180件(2020年10月現在)、打ち合わせの回数は約3,500回に上るそうです。
MEMSは科学技術の観点においても世界中から求められるセンサであると同時に,この技術を開発するにあたって立ち上げられた事業の仕組みについてもまた紹介して頂きました。
この技術が開発されるにあたって日立製作所内に設立された社長直轄の未来投資本部では,MEMSが対応するような社会インフラについての問題のみならず,中長期の視点に立脚して次世代に求められる科学技術やそれらが対応する諸問題を見据え,そのマーケットポジションを確保するための迅速な事業化や投資を検討しながら,ベンチャーを含めた国内外の機関と連携を強化するといったOpen Innovationを実施します。その際,未来投資本部は今後の未来をテクノロジーによって先導するため5つのプロジェクト,「社会インフラ保守」「ロボット/AI」「ハピネス」「デジタル・グリッド」「ゼロカーボン」「エイジングソサエティ」を,それぞれに専任のプロジェクトリーダーをアサインした上で設置し,これらの区分けも随時見直し・追加を図りながら運営されています。
以上のように,今回はMEMSを踏まえての国内外の社会インフラ問題についておよび世界を見据えたこの取り組みを実践する新規事業部の仕組みについて,”リアル”に紹介して頂きました。
II. ToTALだからこそ,拝聴させて頂けたコト:
上記I. (2)でご紹介させて頂いたようにMEMSは世界に名を轟かせるほどの機能を持ち,これによって国内外における漏水問題を解決させることができるだろうという期待を私たちは抱くことができます。しかしながら,このMEMSが開発されるまでに,技術的な問題をはじめ様々な障壁に当あたり、そのときの苦労話についても紹介して下さりました
MEMSをはじめとした漏水センサは地中に存在する水道管から発せられる音とその振動を元手に検知します。しかしながら,他社がこれまでに開発してきた従来の漏水センサはおよそ80%以上もの誤検知の確率にとどまっていました。というのも,漏水センサが注目する水道管以外にも水関係のなかには下水から発せられる音や振動があるのと同時に,それ以外にも自動販売機や人の往来,新しく建物が建築されるという様々な外部要因が存在しているために,これらから発せられる音や振動をセンサが誤って「漏水」と判断して検知してしまうのです。これまでのセンサ開発に携わってきた技術者たちは「漏水の振動だけを判別させることはできない」と,その高確率な誤検知を甘んじて受け止める態勢をとっていたようですが,竹島さんおよびチームは「本当にそうなのか。確かめもせず,諦めてしまってはイノベーションは生まれない」とここで頓挫せず,漏水のみを判別する技術開発に注力します。
この技術開発に際しては試作案としての数多くのアルゴリズムを開発するという高度なテクニックと専門の知識が問われる作業の毎日ではありますが,そもそもの素材として,いわばフィールドワークのような形で多種多様の紛らわしい「振動データ」をひたすたに拾い集るという作業も同時に行われました。ある日,試作のセンサが漏水を検知し,実際に調査会社を派遣して確定調査を行うのですが,なぜか一向に漏水は見つかりません。なぜセンサは反応しているのに実際に漏水していないのかについて調査を実施してみた結果,付近になんと浄水槽が設置されており,そこから発せられる音や振動を漏水と誤判断していたようです。
このような地道な市街地で採取した実測データ元手に一連の開発作業を進めたことが功を奏し,漏水特有の振動を判別する日立製作所独自のアルゴリズムを開発することに成功したのです。上記に記したように,他社によって開発された従来のセンサは80%以上の確率で誤検知してしまい半ば頓挫していたようですが,竹島さん率いる日立のチームによって開発されたこのMEMSは当初の現地実証の結果として誤検知率0%という成績を生み出すことができました。
竹島さんによると,水道管の破損による漏水からは常時一定の振動を検知することができ,このような特性を持つ音は漏水以外にはあまり存在しないとのことです。そのため,「漏水」と判断する際には時間を置いてその波を確認し,そこに一定さが見出されたときにそのジャッジを下すようです。このように考えると見極めるのはそう難しくないのではないかとおもわずの邪推をしてしまいますが,やはり正常の水道管も同じように一定の音と振動を発生させてしまうので,単純に判別することは出来ないとのことです。
III. 筆者の感想:
今回のご講演では、我が国のみならず世界規模の新規事業についてこれまでの軌跡を紹介してくださり,成功と希望の裏にある途方もない苦労や苦しみのエピソードまでをも我々学生に,ありありと伝えて下さりました。
今回参加させて頂いた我々学生も含め、少なからず日本に暮らす全員が水道といった社会インフラの恩恵を授かっています。過去にそのようなインフラ技術を開発・普及することで、0を1,そして100にしてくださった過去の技術者を含め,現在の我々の生活を支えてくれるそのような技術を未来にまで繋げてくれるのが竹島さんはじめ日立製作所のチームです。いま,東工大で研究および研鑽を積んでいる我々学生も、幅広い分野でひとの幸せや健康を支えるために,これまでの産物を継承していき,また,新たな1を創出させていかなければならない・・・・・そのような使命を今回のおよそ2時間の講演で改めて感じられた機会となりました。
今回、我々に話題提供とコミュニケーションの時間を割いて頂いた竹島さん、本当にありがとうございました。
(文責:小埜功貴 環境・社会理工学院/社会・人間科学コース/修士1年/ToTAL 3期生)