2025年7月2日、「プロフェッショナルと価値創造 A」第3回を、ゲストスピーカーとして、宮本侑達医師(ひまわりクリニック/名古屋大学大学院医学系研究科総合診療医学 家庭医療専門医・在宅医療専門医)をお招きし、開催しました。生命理工学コース M1 宮谷明さんが報告します。
| 該当するアントレプレナーシップ科目 | TAL.S502/TAL.S507 プロフェッショナルと価値創造 A/C |
| ゲストスピーカー | ひまわりクリニック/名古屋大学大学院医学系研究科総合診療医学 家庭医療専門医・在宅医療専門医 医師 宮本侑達 |
| 開催日時 | 2025年7月2日(水)18:00-20:00 |
| 開催場所 | S4-201、南4号館2階、大岡山キャンパス |
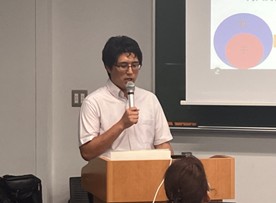

内容紹介
概要
アントレプレナーシップ科目(ToTAl科目)である「プロフェッショナルと価値創造 A」第3回を、対面形式で開催しました。今回は、ゲストスピーカとして、ひまわりクリニック/名古屋大学大学院医学系研究科総合診療医学 家庭医療専門医・在宅医療専門医 宮本侑達医師をお招きし、「診察室で見えた“青年期の壁”―医師の視点で考える、転機を乗り越えるヒント」のテーマで講演いただき、その後、学生との質疑応答を行っていただきました。
尚、今回は、ToTAL OBの篠田泰成さんのご紹介で実現しました。
内容
- 宮本医師について:
宮本医師は、昭和大学医学部を卒業後、亀田総合病院・亀田ファミリークリニック館山で研修を行い、家庭医療や心療内科で幅広い経験を積んできました。家庭医療専門医・在宅医療専門医として、地域に根ざした丁寧な診療を大切にされている。現在はひまわりクリニック・おひさまクリニックで常勤医として勤務中です。当日は、ひまわりクリニックの診療内容の紹介と家庭診療科に進もうと考えた経緯、サービスの概要、理念の紹介、若年層にとって主要な相談内容の紹介などをお話しいただきました。
- 講義の内容について:
- 宮本医師は、アメリカで普及している家庭医療が日本にも定着することで救われる人がいると考えており、枠組みを医師に問わない勉強会の設立、医学論文の発表といった形で啓蒙活動を行っている。彼は臨床医として、浦安にあるひまわりクリニックで在宅医療・心療内科外来を行っており、今回の講演では来診された20~30代の患者さんのお話をベースに病理についてお話をしてくださった。
- 家庭診療とは、子どもから高齢者の方まで、年齢や疾患の境界の枠を超えた診療をメインとしています。宮本医師が大学に通っていた当初は、家庭医診療の研修施設は少なく、当時は知名度が低かったそうだ。この、家庭診療医の持つ専門性であり、強みとするところは、長期間に及ぶ診療を行う都合上、患者さんのライフサイクルの変節を共に過ごす性質があることだそうです。これによって分かった点の一つに、症状を引き起こす遠因となるケースが多く観察されるとのこと。これに依拠して、ライフサイクルの変節時に人の感じる困難の内容を詳細に確認したそうです。これを“乗り越えるべきもの”として見なすのではなく、如何にして「付き合っていくか」と見なすことが重要であるとのこと。
- これの肝要なところは、医療側もこれを意識して患者に寄り添う、肯定すること、並びにこれを解決するためにコアとなる家族の構成員は誰であるかを明らかにするという点とのこと。特に、この家族構成員としての患者という観点は、突発的に話し合いを不利にしてしまうケースもあるものの、根本的解決、議論のフレームワーク変更等において明瞭に関係が見られると考えているとのこと。このことは、宮本医師の公演中でも度々、「問題の解決にはご家族を呼ぶか否かの選択がある」という形での言及がありました。これには、例えば子と親との関係では「子の方の自立」だけではなく、「親サイドの理解」を求めなければならないシーンがあり、お互いの距離感を理解していかなければ解決にはつながらない、といった形で言及がされていました。
- これらを行っていく上で特に重要な関係は、意外にも患者さんにとっての上下関係の薄い「斜め上の人との関係」であるとのコメントがありました。実例として、講演ではサザエさんに登場するカツオくんの視点から見たマスオさんのポジション(叔父さん)との関わり合いの中でこういった関係は模索されるとのこと。
- また、壁との付き合い方において今回あえて紹介くださったケースでは、「こうあるべき」とは異なる解決策と向き合うことも重要であるとお話がありました。この際に適する形を見つけることが大事なのだそうで、内情として重要なのは、当人の特性を受け入れることとのこと。
- このように実際に家庭診療のケースについて講演してくださった宮本医師が、患者さんとの関わりで特に二つ大事にしているとのこと。
一つは共感であるそうです。これは同情とは異なる関係にあるとのこと。宮本医師の定義によれば、「同情」は、相手の立場や気持ちに無理に合わせにいくため、医師の疲労感や患者から見たさいの感情の齟齬の感じやすさなどの問題があるそうです。一方で、「共感」は、あくまでも、相手の立場を理解する行為であり、自分が必ずしも同感であることを意味せず、相手の立場を尊重しつつ話を聞き出しやすい雰囲気作りをする行為とのこと。
もう一つはアサーションという伝え方の工夫です。診療の中でその方法を直接伝えるだけでなく、関連する書籍を紹介することもあるとおっしゃっていました。というのもこの系列の話はとても多くの本が出版済みであるとのことです。
講演後、学生数名と夕食にもお付き合いいただきました。遅くまで、学生と時間共有いただき、ありがとうございました。


報告者
ToTAL 8期生 生命理工学コース M1 宮谷明


