2025年5月31日(土)、6月1日(日)の2日間、科目の第2回として、千葉県幕張にあるクロスウェーブ幕張にて、合宿を行いました。科目としては第2回になりますが、同科目の中身となるプログラム「リーン・ローンチパッド・プログラム(Lean Launchpad Program (LLP) 」としては、プログラムの最初にあたります。ToTAL 8期生・豊田啓介さん(生命理工学院融合理工学系ライフエンジニアリングコース 修士2年)による報告です。
| 該当するアントレプレナーシップ科目 | TAL.W504/505 修士リーダーシップ・グループワーク実践 I/II TAL.W602/603博士リーダーシップ・グループワーク実践 I/II ENT.V205 学士価値創造グループワーク実践 A |
| ファシリテーター | スタートアップ・ブレイン株式会社 堤孝志 氏 |
| メンター | 志村武信(日立製作所、ToTAL OB)、千葉のどか(東京科学大学、ToTAL OB) |
| 開催日時 | 2025年5月31日(土)10:00-19:00 2025年6月1日(日)9:30-17:00 |
| 開催場所 | 千葉県幕張市「クロスウェーブ幕張」 |
前回(第1回)では、プログラムで取り上げる事業アイデアをプレゼンし、その結果7チームが、本プログラムに参加するチームとして選抜されました(セレクションピッチ)。
今回は、選抜された全7チーム(23名)が参加して、1泊2日で研修施設に缶詰状態での作業がスタートしました。セレクションピッチの段階で各チームの方向性やチームワークは殆ど固まっていたので、出だしはどこのチームも順調でした。




第1日
1日目は、顧客の詳細化から始まりました。Eary Adapter (EA)と呼ばれる、製品・サービスの初期の消費者層を明確化していき、どこに需要があるのかを確認していきました。これが意外と難しく、EAの「どんなに高いお金を払ってでも手に入れたい」と思うような動機がなかなか確定できません。
続いてのフェーズはプロモーションである。製品を開発するには資金が必要であり、その資金を確保するためには製品・サービスを、論理的にきっちり説明する必要があります。プロモーションのためのプレゼンテーションと動画を作るのですが、当然開発前なので見せるべき「モノ」がないチームがほとんどであったので、いかに工夫して製品の魅力が伝えられるかが重要でした。翌日朝一の発表会を目指して準備を進めます。
1日目のワークはここまでですが、個人的には、今回の合宿の「本命」はここからです。折角、はるばる幕張まで来たのに、ホテルに閉じこもりきりのはずがない。翌日の発表に向けて残って作業をする他のチームを横目に、我々のチームは「海」を目指しました。そう、ここ「幕張新都心」は臨海都市なのです。幕張メッセやZOZOマリンスタジアムから駅に向かって、帰宅する人々の濁流に逆らいながら、南西の方角にひたすらまっすぐ2-30分ほど歩きました。その先には玄武岩の黒っぽい砂浜と、遥か彼方に見える東京と横浜の摩天楼、そしてコンテナ船が行きかう狭い海が広がっていました。東京湾の夕暮れは貴重な土日を授業に捧げた私たちのやるせない憂鬱を静かに映し出しているようでした。
夕食があるので早々に切り上げ合宿場に戻った。夕食を済ませた後はここぞとばかりに持って来ていた麻雀を広げました。麻雀によってコミュニケーションの活性化を図り、チームの結束力を高める作戦です。修士課程といえどもまだまだ若気のある学生です。遊んでばかりもいられない。なぜなら翌日の発表準備が終わっていないので。他の班が作業を終えて解散するころに、私たちも重い腰を雀卓から上げて準備に取り掛かかります。こういうのは実は日付を越えてからが勝負であったりします。夜が更けていくごとに不思議と高揚感が高まっていく。私たちの強みであるバイタリティを活かして、納得のいくクオリティの資料を完成させることができました。
第2日
睡眠不足ゆえの眠い目を擦りながら2日目の朝を迎える。まずは各班のプレゼンテーションから始まりました。詳細は末尾にまとめますが、どの班も非常にクオリティの高い発表を行っていました。特に動画の方は「実際に製品を使っているシーン」を想像できるような創意工夫がいたるところに見られました。Chat GPTやGeminiといった生成AIによって生成させた画像や動画も多くみられ、先端技術をうまく活用できているなと感じられました。
プロモーション発表が終わった後はビジネスモデルキャンバスと呼ばれる、ビジネスモデルを可視化し、事業計画を整理するためのフレームワークを吟味しました。
このビジネスモデルキャンバスは、主要パートナー、主要活動、主要リソースなど9つの要素で構成されており、これを埋めていくことでビジネスモデルを簡単に把握することができます。これを基に今後改善できる点について議論を重ねた。ここでの議論を通して、これまで漠然としていた事業計画が、具体的な形を帯び始め、チーム全体で共通認識を持つことができました。
ここまで終えたところで2日間の合宿は完走です。朝から晩までLLPに取り組む非常に充実した土日でした。この2日間でまとめた、いわば、顧客のイメージ、及び、ニーズのメカニズムの仮説を、今後の活動で検証し、EA探索を開始します。
この合宿でチームの仲を深めることができたので、最終発表に向けて事業の方針を固めていきます。
各チームの事業概要

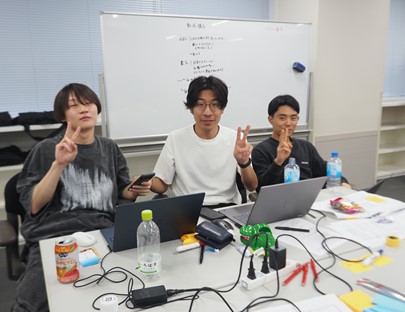
1. aging-meter:
・誰もが気軽に利用できる廊下進行度測定サービス「epigenetic clock TES」を活用し、推奨する老化抑制法を提示するサービス。
・バイオの先端技術を使ったサービスの展開を想定している点が(旧)東工大らしくて面白さがあった。
2. agri:
・深刻な人手不足で収穫ロスが発生しがちな地方農家と、費用を抑えて日本のローカル生活を体験したい外国人観光客と学生をつなぐマッチングサービス。
・生成AIを利用したクオリティの高いプロモーション動画が素晴らしかった。先端技術の応用可能性を垣間見た。
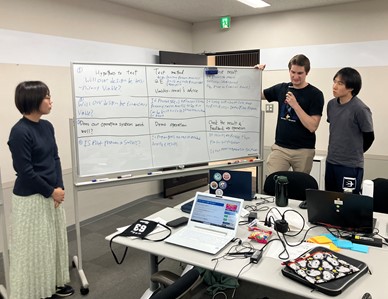
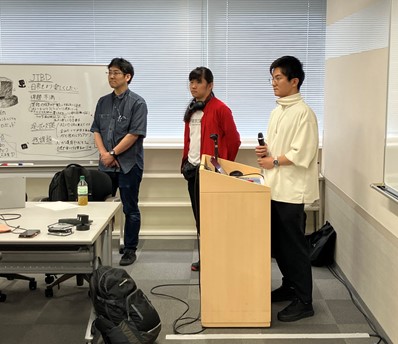
3. Katabuchi-lab
・高断熱性能、簡易組み立て機能、耐震性を兼ね備えた災害時用の個人ブースの開発・販売。
・メンバーの研究分野である断熱材の製品化に取り組んでおり、専門性を強くいかせていた。
4. Sugi Tech
・既存のスマートスピーカーに外付けでき、音声に反応して動きを付加させて暖かみのあるコミュニケーションを実現するデバイスの開発・販売。
・今回LLPでは少数派のモノづくりをするグループではあるが、実現性や利便性・使用感などが詳細に伝わってきた。

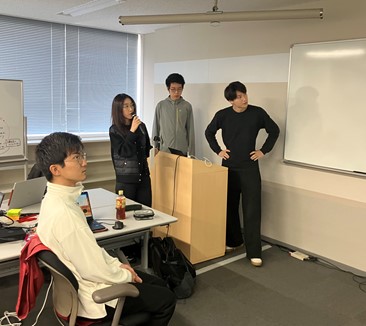
5. JUNCTION HUB
・「人目をきにせずちょっと座りたい」を実現するウェアラブルデバイス「スマートスタンド」の開発・販売。
・筆者である私のチーム。これを実現できる“モノ”を提示できていないのが唯一かつ最大の欠点なので、早急に試作品作成に取り掛かりたいところだ。
6. TSUBAME LAB
・オープンソースで公開されているロボットアームの計測データ、DIYキット、組立済み製品を低価格で販売する事業。
・既に競合がいる製品を扱うグループだった。価格で勝負するらしいので、どういった経営戦略にするのか興味深いところだ。
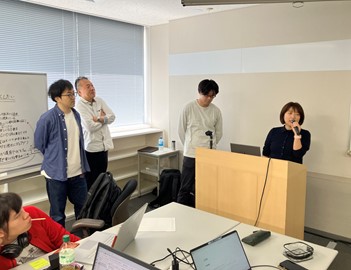
7. Makuhari Kombu
・幕張の浜で筏を浮かべ、コンブやアマモを栽培することで海洋中の二酸化炭素を吸収し、これをカーボンクレジットとして販売する事業。
・ゲストで参加したウェザーニューズのグループである。今回唯一環境問題に関わるビジネスを展開するので、どれだけ需要があるかがみどころだ。
報告者
豊田啓介 生命理工学院生命理工学系ライフエンジニアリングコース M2


