(In Japanese only.)
今期のToTAL科目「(修士・博士)リーダーシップ・グループワーク実践 I/II(S)」のコンテンツであるLean Launch Pad 第5回を2022年7月1日に行いました。
・科目群/Group: リーダーシップ、フォロワーシップ、合意形成/Leadership, followership, and consensus building
・科目/Course: TAL.W505・TAL.W603 修士リーダーシップ実践I/II <S>・博士リーダーシップ実践I/II <S>/ Master’s Practical Group Work for Leadership I/II<S>,Doctoral Practical Leadership I/II<S>
・プログラム名/Program: Lean Launch Pad #5
・開催日時/Date & Time: 1/Jul/2022 18:15-21:45
・ファシリテーター/Facilitator:堤 孝志
- 概要
7月1日(土)に、リーン・ローンチパッドの第5回を行いました。今回のワークショップでは、各チームの進捗報告を行いました。その後は講師から、最終ピッチに向けた説明が行われました。最終ピッチでは、事業プレゼンテーションを行ってもらいます。今まで行って来た進捗報告とは違って、初対面の人々に事業の蓋然性と成長性を伝えることが目的です。今回のワークショップでは事業プレゼンテーションの前半部、事業の蓋然性を伝えるためのプレゼン方法が説明されました。
- 各チームの進捗報告
STEPS (Feelingram) (橘川侑生、吉良真由子、松沢純奈、藤本清也)
・事業内容:記念日をお祝いするレストランをスマートに見つけることができるアプリケーションです。
・発表内容:「人それぞれに異なる”ちょうどいい”を基準にしておすすめのお店やお料理を探すことができるアプリケーション」からピボットしました。30~40代の働き盛りの既婚男性をターゲットしています。
Otononiwa (深井悠太郎、金雯、足立零生、野本周平)
・事業内容:作詞家が詩を投稿し、作曲家と共同で曲を作成できるプラットフォームアプリケーションです。
・発表内容:ビジネスの初期段階では作詞家のみをEarly Adopters(以下EAと略す)として、焦点を当てることに決めました。作詞家は、好きな作曲家にお金を払い自分の詩に合わせた作曲サービスを受けます。これは、お金を払って作曲のサービスを受けたい作詞家EAが見つかったためでした。また、3年後に収支均衡に至る収益モデルを発表しました。


(左から、Steps、Otononiwa)
Poetry Factory (山本薫、船岡佳生、古林捷)
・事業内容:好きな詩がプリントされた包装紙をカスタマイズして購入できるサービスです。
・発表内容:顧客セグメント分析よりEAの詳細化を行いました。また、2ヶ年計画の収益モデルを立てました。
Process (高橋健一郎、横尾幸丸、長谷川貴弘)
・事業内容:完成された芸術作品だけでなく、制作過程も購入することで芸術家を支援できるサービスです。
・発表内容:作品制作を発信する芸術家EAのインタビューを行いました。また、制作を支援する側(購入者)のEA特性の詳細化を行い、「アートを理解したいけど,アートが分からない人」をターゲットにインタビューを実施する予定を立てました。
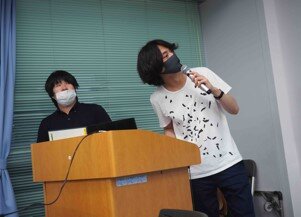
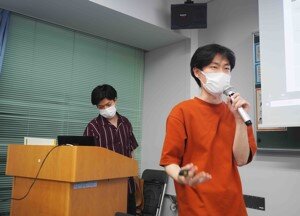
(左から、Poetry Factory、Process)
Amigo (Gecchele Marcello、Goo KangWei、河村毬絵、Brandon Lieberman, Shakeel Muhammad)
・事業内容:外見による偏見なしに、同じ趣味を持った友達と出会えるソーシャルアプリケーションサービスです。趣味活動に必要な器材を販売するローカル店と連携し、ローカルイベントへの参加ができることが特徴です。
・発表内容:本サービスに興味を持ったインタビュアーのセグメント調査からEA検証を行い、5年後に収支均衡に至る収益モデルを立てました。
Arashi(Realrime translation) (Leo Sylvia、加藤祐介、毛利友揮、大野哲史、徐書雅)
・事業内容:日本語に困っている在日外国人向けに、カジュアルなリアルタイム通訳を提供できるアプリケーションサービスです。通訳資格を持っていない人でも通訳者になれることが本サービスの特徴です。
・発表内容:決定したMVPに従うデモアプリケーションの作成を行い、3年後に収支均衡に転じる収益モデルを立てました。


(左から、Amigo、Arashi)
Freehand (丸山 裕生、長尾 優真、高島 空良、友利 優希、甲斐 晟豪)
・事業内容:ゴミ箱を私有地に置くことにより、誰もがゴミを有料に捨てることができると同時に、広告主が広告するゴミ箱を提供、管理するサービスです。
・発表内容:土地主との収入モデル、個人ユーザーとの収入モデルを定立し、2年後には収支均衡に転じる収益モデルを発表しました。
Digital Indian Restaurant (原口 陽菜)
・事業内容:忙しい人向けに、希望に合わせた食事を提供するサービスを開発しています。
・発表内容:サービスをピボットしました。
Outa’ (小埜 功貴、三宅 勇太朗、野村 優華、岡野 めぐみ、大熊 日奈子)
・事業内容:男性として経験する「生きづらさ」を解決するサービスを開発中です。
・発表内容:サービス詳細をピボットする目的で、チーム内での議論を続いています。


(左から、Freehand、outa’)


(左から、Digital Indian Restaurant/Haraguchi、Kim & Rath)


(左から、TA/Morimoto、TA/Chiba)


(左から、Commentator/Hirai、Facilitator/Tsutsumi)
- 最終ピッチプレゼンテーションの方法 - 前半部
最終ピッチでは事業プレゼンテーションを行います。事業プレゼンテーションは、投資をもらうためにベンチャーキャピタルに発表したり、ビジネスコンテストで賞をもらうために発表したりするケースが考えられます。前半部ではまず、ターゲットとしている顧客が直面している問題を取り上げ、彼らの問題が解決できる自社の商品やサービスのデモを紹介します。ここで、抽象的な表現をできるだけ避けて、early adopterの詳細な特性を分かりやすく説明することが重要です。次には、商品の実現性をエビデンスを持って示し、稼ぎ方、マネタイズの仕組みを紹介します。同じ商品であっても、マネタイズする仕方は様々でありうることから、マネタイズ計画も事業の重要な要因です。前半部で発表する最後要素は、なぜこの商品が爆発的に売れるのか、その理由を伝えることです。インタビューから分かったearly adopterがエビデンスになります。しかし、「インタビュアーのn%が買いたいと応答」だけでは、early adopterの存在の根拠にはならないために説得力が落ちます。また、関連する市場の統計だけでの説明も絶対に避ける必要があります。以上の構成が、今回のワークショップレクチャーで説明頂いた、前半部プレゼン方法です。
- 自分の学び
約2ヶ月間ともチーム員が協働して、同じ目標を共有しながら事業案を具体化させて来ました。研究室では、先生のアドバイスに従ってやることが決まったり、自分が文献調査を行って自律的に選定してきたりしたわけですが、本プログラムではチーム員の意見を発散させ、それを具体的な案にまとめる必要があります。同等な関係の人たちが集まって、意思決定をしていく本プログラムは研究活動とは違うことから、私にとって大事な体験であり、大切な学びにつながりました。今回の授業では多くのチームがピボットを行いましたが、チーム同士のアイデア作りの試行錯誤を反映しているのではないかと思います。本プログラムを通じて、チーム員とのコミュニケーション能力向上につながると感じました。
- 終わり
次回は、第6回目です。事業プランを詳細化させていきながら、ベンチャーキャピタルを聞き手と想定して発表プレゼンを準備して行きます。素晴らしい事業案が出来上がるでしょう。
(文責:金俊熙 工学院 機械系ライフエンジニアリングコースD2、ToTAL 3期生)


