(*In Japanese only.)
今期のToTAL科目「(修士・博士)リーダーシップ・グループワーク実践 I/II(S)」のコンテンツであるLean Launchpad 第6回を2022年7月15日に行いました。
・科目群/Group: リーダーシップ、フォロワーシップ、合意形成/Leadership, followership, and consensus building
・科目/Course: TAL.W505・TAL.W603 修士リーダーシップ実践I/II <S>・博士リーダーシップ実践I/II <S>/ Master’s Practical Group Work for Leadership I/II<S>,Doctoral Practical Leadership I/II<S>
・プログラム名/Program: Lean Launchpad #6
・開催日時/Date & Time: Jul.15th,2022,18:15-21:15
・ファシリテーター/Facilitator:堤 孝志 (ラーニング・アントレプレナーズ・ラボ(株))
1.当日の活動の概要
事業創造を行うワークショップ「Lean Launchpad」の第6回を7月15日に行いました。次回が「デモ」を行う最終回となるため、各チーム、2週間後に控えている最終のピッチに向けた準備も含め、各チームの進捗報告と講師の先生や他のメンバーからのフィードバック・質疑応答が主な活動でした。また、授業の最後には、第5回に引き続き、最終回での事業プレゼンテーションの構成における、事業拡大や成長性の部分について、堤さんから講義がありました。
各チームの発表と質疑応答では、今回の講義の内容とは対照的に、事業が軌道に乗るまでの段階で要となる、アーリーアダプター(以下EA)の具体性、顧客が抱える課題とその解決策がいかに合致しているかといった点を中心に盛んに議論がありました。


2.当日の活動の概要
( 1 ) STEPS ( 橘川 侑生、吉良 真由子、松沢 純奈、藤本 清也 )
〜どんなに忙しくても焦らず慌てず予約できる〜
・事業内容:記念日のリマインダーと、記念日をお祝いするためのレストラン探しに特化したアプリケーションを開発しています。
・発表内容・進捗:日付・沿線・ジャンル・予算を元にレストランを検索できるプロトタイプの表示、テキストマインニングを通じたレストランの検索方法、顧客候補へのインタビューを元に、顧客となりうる人、ならないと考えられる人の特徴のまとめを中心とした発表をしました。

( 2 ) Poetry Factory ( 山本 薫、船岡 佳生、古林 捷 )
〜詩おくり〜
・事業内容:ユーザーが贈りたいプレゼントに合った”詩”が描かれた包装紙を提供、発送するサービスです。
・発表内容・進捗:前回までの内容に加え、シーンや作者などから詩を検索するプロトタイプの実演、詩のデータベースの構築と管理の方法、材料費などの具体的な初期費用などについて説明しました。

( 3 ) Process ( 高橋 健一郎、横尾 幸丸、長谷川 貴弘 )
〜プロセスを知りアートの価値を理解する〜
・事業内容:絵画の創作活動において、芸術家は作品と共に製作過程を公開し、顧客は制作過程をもとにアートの価値を学び、制作過程にある作品も購入できるプラットフォームを開発しています。
・発表内容・進捗:芸術家、顧客側それぞれの画面操作のデモを公開しました。また、インタビューから、顧客となりうる人は、「作品の購入にあたり制作背景を知ること」を重要視していることを指摘しました。

( 4 ) Freehand ( 丸山 裕生、長尾 優真、高島 空良、友利 優希、甲斐 晟豪 )
〜どこでもすぐにゴミを捨てられる自由〜
・事業内容: ユーザーに向けては、有料で街頭に設置されたゴミ箱に手持ちのゴミを捨てることができるサービス、設置者としての顧客にはゴミ箱の提供・ゴミの回収と引き換えに広告機会や費用が支払われるサービスです。
・発表内容・進捗:街中で出たゴミをどのように捨てるのかのシミュレーション動画の紹介、顧客候補層へのアンケート結果を踏まえ、顧客となり得る大学生や社会人の具体例、収益の大まかな仕組みを紹介しました。

( 5 ) Team Arashi ( Leo Sylvia、加藤 裕介、毛利 友揮、大野 哲史、徐 書雅 )
〜いつでも、どこでも友達に聞くみたいに翻訳を得られる “グルグルtalk”〜
・事業内容:日本に住む外国人に向けて、細かいニュアンスまで含んだ、正確な通訳をリアルタイムで提供するサービスです。
・発表内容・進捗:実際の翻訳製品の動画は制作中であり、「仕組みと実現性」という観点において、ユーザーと翻訳者のマッチングの仕組み、通話や決済の技術的な枠組み、さらには、マネタイズのイラスト化やEAのニーズと価格のバランスの見直しについて紹介しました。
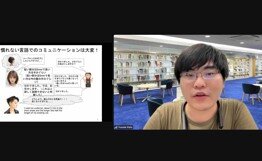
( 6 ) Outa ( 小埜 功貴、野村 優華、岡野 めぐみ、大熊 日奈子 )
〜自他ともに認められる”自分推し”ファッションと出会う機会を提供〜
・事業内容 :男性に向けて、他者からも認められ、自分も心から「好き」だと思えるファションを提供するサービスです。
・発表内容・進捗:ピボット前のアイデアに加えて、”自分推し”の服として取り扱うファッションの範囲、仕組みとマネタイズの方法、EAとなる人物像の見直しについて発表しました。また、”自分推し”と関連して、Z世代の男性が抱える「理想の男性像」についても言及しました。

( 7 ) Team Haraguchi (旧 Digital Indian Restaurant) ( 原口 陽菜 )
〜家族の食事管理を手助けするECサイト〜
・事業内容:家族の構成、体質、嗜好などの特性に合わせた食材の注文受付・配送サービスの開発を行っています。
・発表内容・進捗:焦点を当てる顧客像、具体的には、家庭環境や食事事情などを具体的に考えました。サービス内容についても、糖質制限やアレルギー対応など、顧客や家族の体質・希望をインプットして食材を紹介して発送まで行うというアイデアを発表し、想定される競合相手も共有しました。

( 8 ) Amigo ( Gecchele Marcello, Goo Kang Wei, 河村 毬絵、Brandon Lieberman、Shakeel Muhammad )
〜New hobbies and new friends〜
・事業内容:外見ではなく、同じ趣味を持った人と出会うための機会を作るアプリケーションを提供します。
・発表内容・進捗:前回はアプリの登録方法を紹介していたのに対し、今回の発表は、イベントの企画方法のデモや、マネタイズのアップデートに焦点を当てていました。

3.自分が学んだこと
前回の講義からオブザーバーとして参加させていただいていますが、明確なEAを見つけることに難航しているグループが多い印象を受けました。
今回までのLean Launchpadの活動や講義を通じて、私は、新しいビジネスを考えるにあたり、大切なことは主に次の3点だと考えています。それらは、「他のサービスでは実現できない何らかのオリジナリティーを創造すること」、「確実にEAとなる人を見つけること」、「EAとなる人が本当に解決したい課題を解決できるサービスを自分たちで制作できること」です。
この中でも、2点目の「確実にEAとなる人を見つけ出すこと」が最も重要であり、難しいハードルだと感じていますが、難しくしている背景の1つとして、後々の売り上げのことを気にして、より多くの人に使ってもらえるサービスにしようとしている部分があるのではないかと感じています。万人受けしそうなサービスを作ろうとすることが、必ずしも問題ではありませんが、多くの人が「求めそう」なことを足し合わせた結果、「そのサービスがぴったりだ」と思う人が誰ひとり現れない事態になりやすい点をよく理解しておくべきだと感じました。

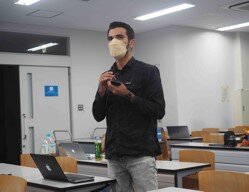


私自身、EAが見つからない問題の解決策は、「とにかくたくさんの人にインタビューする」、「顧客が抱える課題を解決するサービスを忠実に再現する」が代表的な方法だと思っています。その一方で、私がグループの一員として活動していた時、EAとなる可能性があるかどうか分からない人に、サービスに関するインタビューを1件するだけでも1時間以上の時間を要した経験がありました。これは、他のグループの方にも共通して言えることだと思いますが、EAをひとり見つけるだけでも、多大な労力は避けては通れないことを、Lean Launchpadを実際にやってみて痛感しました。
あくまで、私個人としての意見ですが、EAを見つけ、製品を作り、成長性を持ったビジネスモデルを証明するといった部分まで妥協なく取り組もうとした場合、履修前に想像していた以上に、相当なモチベーションと時間が必要になります。実際に、昨年度、参加された先輩からは、「Lean Launchpadでのプロジェクトの実現を最優先にすると、研究と両立することも難しいくらいだった」というお話も聞きました。ある面、脅しのような文言になってしまいましたが、私自身が研究や資格試験の勉強とLean Launchpadの両立に失敗したこともあるので、来年度以降に履修される方は、「時間と気持ちに余裕を持ってこの講義に臨まれると良いと思います」というアドバイスを、ここに残しておきたいと思います。
Lean Launchpadの本筋から外れてしまいますが、私自身は、この講義と他の活動の両立に失敗した経験から、「自分が使える時間」、「絶対に取り組まなければいけないこと」、「こだわりを持って取り組みたいこと」を軸に優先順位を立て、1つの物事に対して、自分が満足にやり切れる時間を作ることの大切さを、身をもって学びました。幅広く教養を身に付けることも大切ですが、これからの私は、「1つの物事に対する収穫を信じ、腰を据えて集中する経験」を積むことを最優先にToTALの活動や、研究活動に臨みたいと思います。
(文責:渡辺 佑、環境・社会理工学院 融合理工学系 地球環境共創コース M1、ToTAL 4期生)


