(In Japanese only.)
ToTAL科目「プロフェッショナルと価値創造 II第5回:「アントレプレナーシップでイノベーションを加速しよう」を2021年1月15日に行いました。
・科目分類/Group of Course:社会課題の認知 /Recognition of Social Issues
・科目名/Course: TAL.S502 プロフェッショナルと価値創造 Ⅱ / Professionals & Value Creation Ⅱ
・プログラム名/Program:アントレプレナーシップでイノベーションを加速しよう/ Driving Innovation through Entrepreneurship
・ゲストスピーカー /Guest Speaker: 倉林陽、Managing Partner(学術博士)、DNX Ventures / Dr. Akira Kurabayashi, Managing Partner, DNX Ventures
・開催日時/Date & Time: 15 /Jan (Thu) 18:00-20:00
2021年1月15日(木)Zoomにて、DNX Venturesマネージングパートナーの倉林陽さんをお招きし、「起業家(企業家)精神でイノベーションを加速する」をテーマに、最新のSaaS(Software as a Service)分野のstart up状況、日米start up 企業への考え方、ベンチャーキャピタル(VC)の役割などの話題提供をいただき、その後、学生とのディスカッションを行っていただきました。日本とアメリカで業界をけん引するベンチャーキャピタリストとして活躍している倉林さんから、前半部分では、倉林さんやその周りの方々が行っているVCの仕事内容、アメリカのスタートアップの現状を話していただきました。後半は、これまでの話を踏まえて考えられる日本とアメリカの違い、これからの日本や日本の企業が抱える課題などをお話いただきました。また、学生からの質問にも丁寧に答えていただき、スタートアップという熱意溢れる業界の一端を感じられる時間を過ごせました。
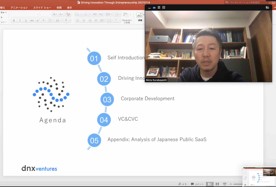

1 VCの仕事:
VCとは、ベンチャー企業やスタートアップ企業など、高い成長が予想される企業に対して投資を行う、出資会社を指します。まだ上場していない企業を発掘して評価を行い、投資を行います。投資を行う前はもちろん、投資を行った後もその企業が成長できるよう、様々な支援を行うのが特徴であり価値です。倉林さんは、数種類のファンドを持ち、SaaS(Software as a Service)業界を中心に投資、スタートアップ支援を行っております。
2 アメリカのスタートアップ業界とVC:
現在の企業の時価総額ランキングを見ると、Big Techとよばれるアメリカのテクノロジー会社が上位を占めており、さらに近年、その上位四社;Google, Amazon, Facebook, Apple、の時価総額は、日本全体の企業の総時価総額を超えてくるほど大きく成長し、日本企業が太刀打ちできない状態となっています。その理由としては、古い企業を新しいスタートアップ企業が追い抜くという文化的背景が考えられるようです。また、アメリカの新規上場企業のうち43%がVCの支援を受けた企業であり、その企業が新規企業の総R&D研究開発費の82%を占めていることを示していただきました。この背景には、新たな課題を見つけ、リスクをとることが当たり前と考える、年齢を気にしないことが多いアメリカ文化が大きな影響を与えているのではないかということで、いかにスタートアップの支援や若い人材に操縦桿を握らせることが大切かを力説していただきました。
3 スタートアップを取り巻く環境の日本とアメリカの違い:
現在、海外から日本のスタートアップが評価され始め、彼らの調達額が増えてきています。しかし、それでもまだ様々なアメリカとの違いが存在するのは確かです。その違いを、三つに分けて説明していただきました。一つ目はアメリカでは経営者の持ち株率が低いことです。これにより、優秀ではないことで経営者が変えられてしまう危機感が生まれ、成長するといわれています。また、創業者と経営者を分けることができ、経営は経営が上手な人が担うことができるというメリットもあります。二つ目は、アメリカで上場するのに必要な売上高が日本の10倍高いことです。上場するハードルが高いため、ビジネスモデルが確立していない状態での上場を避けることができるようです。三つ目は、M&Aに対してポジティブな考え方をしている点です。資金のある大企業は、スタートアップを買い、その事業をこれまでの事業とリンクさせたり、別に買収した事業とつなげたりします。また、買収した企業の経営者を事業リーダーとして雇うことで、さらに事業が進歩していくようです。このような考え方は、まだ日本では根付いていないようです。このようなサイクルがあることで、アメリカではスタートアップが成長しやすい環境にあるといえます。
しかし、日本にもスタートアップの種はたくさんあります。名刺管理や勤怠管理といったサービスはアメリカのビジネス習慣や管理業務からは決して生まれず、日本だからこそ生まれるビジネスチャンスといえるでしょう。だからこそ、日本のスタートアップの構造自体を変えて、伸ばしていきたいとおっしゃっていました。
4 これからの日本のスタートアップ:
ベンチャーへの投資は、成功している一握りの人間が大きく成長し、その他はほとんど成功していないという現状があります。その背景にはベンチャーキャピタリストはVCや起業家との業界⼈脈のどのくらい中⼼にいるか(中⼼度:Centrality)が極めて重要である、とおっしゃっていました。また、デジタル化に伴うSaaSが大きな波となっていること、人材やインフラが充実してきたこと、東証マザーズが存在することなどで、成長しやすい地盤も整ってきました。これらを受けて、現在、日本のスタートアップは大きく進化しているということも言及していました。巨額の資金流入、起業初心者が多い点に注意すれば、さらなる発展が期待できると聞き、私たちも聞いていて胸が熱くなりました。
最後にCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)の話をしていただきました。日本における伝統的な企業ではスタートアップと文化が違うので、それへの支援がうまく機能しないことは多いとおっしゃっていました。業界の中心に立ち、スタートアップ企業の株主になるということは、投資先の企業価値を向上させることに全力をささげる気概のあるVCでないと、投資先を成長させることはできないと聞き、全力をささげているからこそ出る言葉に身が引き締まる思いになりました。
5 Q&A:
お話の最中にも学生から質問がありましたが、最後にQ&Aの時間を設けていただきました。倉林さんやほかのVCの方が持つ強みや人間性の部分や、人を巻き込む人の共通点などの特徴などを語っていただきました。自分なりのリーダーシップを探している私たちにとって、大きく参考になる話を聞くことができました。
6 感想:
リーダーシップ教育院の終了審査員も務めていただいている倉林さんのお話は、冷静に日本とアメリカを比較して日本の課題点を浮き彫りにしている反面、情熱に満ちていて日本のスタートアップ業界を伸ばしていく気概を感じるものでした。私たちも、倉林さんのように自分に信念をもって、目的意識を忘れずに様々な活動に取り組んでいきたいと思います。
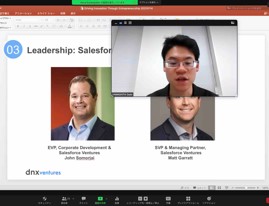
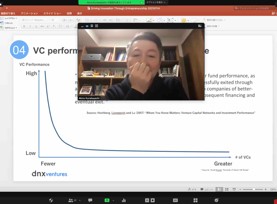
最後になりますが、お忙しい中、このような機会を提供してくださった倉林さん、心よりお礼を申し上げます。
(文責:山下大貴 物質理工学院 材料系材料コース M1、ToTAL3期生)


